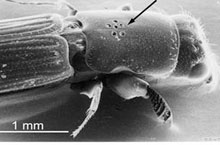林業・木材講座 8 ナラ枯れ
① 被害の状況
全国的な被害については、平成22年に過去最大の被害量(約33万㎥)を記録して以降減少しているが、被害府県数は増加している。
東北地方では、平成28年の被害量が、宮城県を除き増加した。
岩手県では、平成22年に奥州市で初めて被害が確認され、平成28年度は、9市町に被害が拡大している。(図1)
② 被害の対象
被害を受けるのは、本州ではナラ類であるが、九州ではシイ類やカシ類にも発生する。ミズナラ、コナラ、カシワ、クリなどのナラ類の中でも特にミズナラへの被害が多く、枯死する割合も高い。
被害木は、夏に突然に葉が枯れる。多くの事例から、最初に被害を受けるのは付近で最も大きな木であることが分かっている。
当初は1本だった被害は翌年以降付近に拡大し3、4年後には集団的な被害となる。従来の被害ではその後徐々に終息に向かい、5、6年後には発生は終わっていたが、最近ではこのような集団があちらこちらに発生し全山に拡大している。
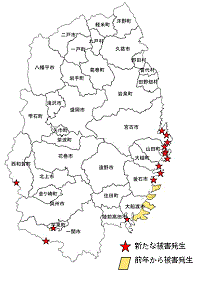
図1 平成28年度
岩手県民有林の被害箇所